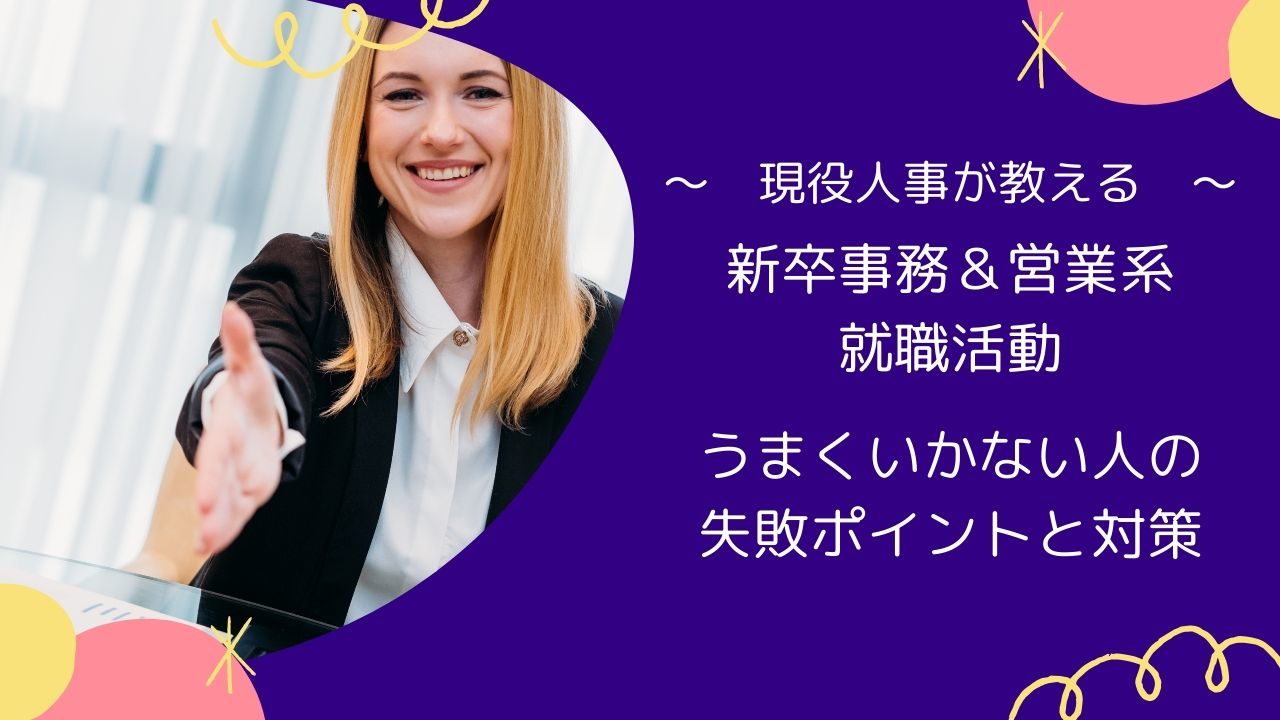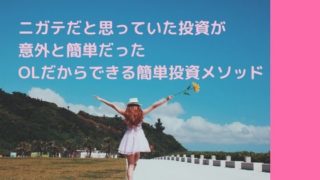Contents
- この記事を書こうと思ったきっかけ
- 面接でわかる「就職活動がうまくいかない原因と対策」
- まとめ
この記事を書こうと思ったきっかけ
就職活動がうまくいかないと、周囲が内定を取っていく中、焦る気持ちだけが大きくなり、このままどこにも就職できなかったらどうしようと、絶望的な気分になりますよね。
しかも、転職とは違い
日本の新卒就職活動市場は、時期が決まっていて、短期集中で結果を出さなければ就職浪人になってしまう可能性が高いことも、焦る要因の1つです。
チャンスを逃してほしくない
今回、この記事を書こうと思ったきっかけは
私自身、15年以上、人事のお仕事をしてきて、実施してきた面接の数は、何千件になり、多い時は、中途採用の面接だけで年間300件ほどこなしてきました。
その結果
うまくいかないポイントが、面接をしただけで手に取るようにわかるので
これまでのデータベースをもとに、少しでも就職活動を満足して終えられる人が増えるといいなと思ったからです。
就職氷河期がやってくる
2020年までのここ数年は、超売り手市場が続いていましたので、かなり容易に内定が取れる傾向がありました。
ただ、コロナ騒動以降の数年は、就職氷河期が到来することが予測され、非常に苦戦する人が増えるだろうと予想していますが
超売り手市場だった時とは、状況が一変していますので、身近な先輩の就活体験は参考にならない可能性があるのです。
私自身の超就職氷河期の経験と、15年以上の人事経験をふまえて、就職活動をする方々の参考になればと思っています。
また、知り合いの方限定でしかやっていませんが、先輩や上司の息子さんや娘さんの就職活動の対策も請け負っています。
教える中でこちらも教わるところが多く、つまづいてしまう傾向なんかもよく似ていることにも気が付きました。
ご本人が優秀だったこともありますが、指導の結果、皆さん、希望していた大手企業数社から内定をもらっています。
なかなか対面で実施する時と同じようには伝わりにくいかもしれませんが、知り合い向けにアドバイスしていることをココでもご紹介しますので、就活成功の糧になればと思います。
面接でわかる「就職活動がうまくいかない原因と対策」
就職活動がうまくいっていない原因を面接の中で探していくと、次の9つが挙げられます。
①と②が最も大切な項目になり、この2つができていないと、就職活動が失敗する確率は非常に高くなります。
- 自分自身がどんな人材であるかをきちんと説明できていない
- どんな仕事がしたいのか、なぜその仕事がしたいのかを説明できていない
- 「御社が第一志望です!」とアピールするが、企業研究が全然できていない
- とにかく入社したら頑張るとアピールする
- 誰よりも御社に入りたい気持ちは強いとアピールする
- 少し厳しめの質問をされたらキレる
- 思ったように話せず、テンパってしまい泣き出す
- 本当に知りたいと思っているとは思えない質問をする
- 面接の中で自身の評価を非常に気にする・求める
- そもそもエントリーする会社が少なすぎる
思い当たるポイントはありましたか?
もし、思い当たるポイントはないのに、うまくいっていないということであれば、気が付いていないかもしれませんが、①が該当するのではと思います。
これまで見てきた中で、一番多いケースが、①「自分自身がどんな人材であるかをきちんと説明できない」なのです。
では、それぞれのポイントについて解説してきましょう。
1.自分自身がどんな人材であるかをきちんと説明できていない
これは、自分自身では一生懸命、自己分析をしたつもりでも、実は深く分析できていないケースが多くあることが原因です。
自己分析って、実は、結構難しい作業なんです。
なぜなら・・・
自分自身は、自分のことをよく知っているのだから、うまく面接官に伝えられていると思ってしまっているのですが
知っていることと、他者に説明できるレベルで言語化できていること
この2つには大きな違いがあります。
また、自分自身では「当たり前」だと思っていることは敢えて表現しないので、大切なそれぞれの個性をうまく表現できていなかったりします。
また、他の人との違い(差別化できるポイント)についても、意識していないことが多く、気が付いていないというケースも多くみられます。
これまで、対面でアドバイスしてきた人達の中でも、一番手をかけたのが、ココでした。
自己分析ができれば、この後の②の解決のきっかけになります。
自己分析をしっかりとできれば、就職活動対策の8割は終わったと思っても過言ではありません
詳しい自己分析のやり方は、別の記事で公開予定ですので、少々お待ちください。
2.どんな仕事がしたいのか、なぜその仕事がしたいのかを説明できていない
働いたことがない中で、どんな仕事がしたいのかを決めることは難しいかもしれませんし、入社する前から、希望する企業の仕事内容をすべて理解することは難しいですが
まず根本的に、どういった仕事が自分に向いているのか、どういった仕事を自分がやりたいのかを理解するところから始める必要があります。
つまり、①でお話した「自己分析」に戻るわけです。
具体例をあげてみましょう
例えば、簡単な例を挙げてみましょう
よく就活のアピールポイントの中にも出てくる「人と接する仕事」について考えてみたいと思います。
仕事をする中で、「人と接することがない仕事」というのは、存在しません。
なにかしらの形で、人と接しながら仕事を進めていくことになるわけです。
ですので、「人が好きだから、人と接する仕事に就きたいです」とアピールするのであれば、どういった人との接し方を好むのかということを掘り下げる必要があります。
どういった仕事がしたいのか・どういった仕事が自分に向いているのか
まずは、どういう仕事をしたいのかを考えて企業を選ぶと思いますが
選ぶ際には、どういう業界でどういう仕事(職種)を希望するのかを掘り下げていくことになります。
つまり、業界研究と職種研究をする必要があります。
実は、事務&営業系職務の面接に来る人の9割以上が営業職を志望しています。
もちろん、営業職は素敵な仕事ですが、営業職ひとつとっても、その内容は様々です。
- 法人向け(B to B)・一般消費者向け(B to C)
- 新規開拓・既存顧客
だからこそ、どんな業界でどういう営業がしたいのかを掘り下げていく必要があります。
どのように掘り下げていくのかというと
自己分析をする中で、自分がどういった時に「やりがい」を感じ、どういった時に「モチベーション」があがるのかが、自分がどういった仕事をしたいという答えを見つけるカギになります。
最近は「働き方」にも注目すべき
少し余談ですが、最近では、会社を選ぶ際に、社員の方がどういった「働き方」をしているのかについても、着目した方がいいと思います。
昭和・平成・令和と、時代が移り変わる中で、その時代の変遷についていけない企業というのは、まだまだ存在します。
夫が夜遅くまで働き、妻が家事育児をするという役割分担時代のマインドが色濃く残り、ワークライフバランスとは無縁の会社もまだまだ多くあります。
夫婦で共に働き、お互い尊敬しあい成長していく、そんな令和の時代の生き方を私は目指したいなと思っています。
まずは、自分自身がどういった働き方・生き方をしたいということを明確にするところから始めましょう。
また、コロナ騒動が起きてしまったことから、各企業の対応にも大きな差が出ていますので、こういった点も実は大切ですね。
3.「御社が第一志望です!」とアピールするが、企業研究が全然できていない
ここからいくつかは、面接での発言から見える失敗の傾向について、書いていきたいと思います。
面接での発言の中で、かなりのケースで使う言葉ですが、使う際には気を付けておかないと、マイナスな印象を与えかねません。
第一志望と言うのであれば
希望する企業の何が魅力的で、どんな仕事がしたいから志望しているのかを明確に伝えられるよう準備しておかないといけません。
また、他の企業と比べ、どういう点に魅力を感じているから第一志望であると理由がないと、第一志望であることの説得力はないですよね。
最近は、超売り手市場だったこともあり、この辺りの準備ができていない人が多く見受けられます。
4.とにかく入社したら頑張るとアピールする
③より悪いケースです。
これは、とにかく事前の準備(自己分析や企業研究)をしていないとわかる人に多い発言です。
できれば面倒なことはしたくないということがにじみ出てしまっていて、また、手っ取り早く面接官から答えを引き出し、それに沿って回答しようとする人もいます。
- 新卒には何が求められてますか?
- どんな人材が御社は欲しいですか?
これらを聞き、そういった人材であることをアピールするのです。
入社したら頑張る気持ちは、みんな一緒です。
そうなると、入社したら頑張ることは当たり前なので、評価の対象にはなりません。
むしろ、この発言をすることで、あまりよく思考できない人物であるという印象を与えるので、「頑張る」という言葉の使い方には気をつけた方がいいでしょう。
5.「誰よりも御社に入りたい気持ちは強い」とアピールする
この言葉は、使い方によっては、④よりもさらに悪い印象を与えます。
みんな入りたい気持ちは同じです。
自分が一番強いというのは、証明のしようがありませんし、④で解説したのと同様に、何も考えてないなという印象を与えてしまう可能性のある言葉です。
残念ながら、思いの強さだけで採用できるほど企業は簡単ではありません。
このアピールをするのであれば、この言葉の理由になるエピソードが必要です。
何があったからその企業に強い思い入れがあるのか、強い思いがある背景を説明できれば、このアピールも有効です。
6.少し厳しめの質問をされたらキレる
世間の風潮として、怒られること・叱られること、厳しく指導される機会が減っていることもあり、少し厳しめの質問をしただけで、明らかに不満が顔に出る人がいます。
また、ムキになって反論してくる人もいますが、大抵の場合は、厳しい状況の際に、どういう出方をするのかを見ているケースが多いので、この時の反応には注意しましょう。
私が勤める会社では実施していませんが、「圧迫面接」も一つの面接手法です。
ビジネスをしていく以上、優しい相手ばかりではありませんし、ストレスのかかる仕事があるのも事実です。
肝心の場面でキレやすい人物というのは、企業としての信用を失う可能性もあり、非常にリスキーなので、企業としてはそういった人材を排除しておく必要があるのです。
圧迫面接はストレス耐性や、そういった場面での相手の出方を見るのに使われます。(個人的には好きではありませんが)
これは、不意打ちをされ、咄嗟に出てしまうものなので、特に意識しておきましょう。
7.思ったように話せず、テンパってしまい泣き出す
多くはありませんが、たまに面接でこういった人がいますが、泣くのは絶対的にNGです。
圧迫面接をしているわけでもないので、多くの場合は、自身の準備不足の不甲斐なさで悔しいと言って泣かれることが多いです。
面接は毎回一発勝負です。
そして、新卒就活は、実施の時期もわかっているので、準備の時間も皆平等に与えられています。
自分自身が準備に時間がかかるタイプなのであれば、そのために何をするべきかを考えて対策を打つ必要があります。
どんな言い訳をしようとも、勝負のタイミングで力が発揮できなかった原因は、間違いなく自分にあるのです。
誰でも準備すれば、きちんと自分をアピールできるようになりますので、後悔のないように、きちんと準備して臨みましょう。
8.本当に知りたいと思っているとは思えない質問をする
面接の時間は、各企業によって様々ですが、最終面接に進むまでは、ほとんどの場合、10分~30分くらいのケースが多いかと思います。
その限られた時間の中で、自身の魅力を伝える必要があります。
質問の時間をもらえない時もありますが、質問の時間がある場合には、質問の内容も評価の対象になっているので注意しましょう。
1~2割くらいの人が、就活対策本で読んだであろう、経営戦略に関すること等、教科書のような質問をされます。
本当に興味があるのであれば、もちろん全然OKですが
「どうしてそれが気になったのですか?」と聞くと、ほとんどのケースは答えられません。
質問のための質問を準備してきていることがバレてしまいます。
面接官は質問の内容からも、その人の思考力や着眼点などをチェックしています。
私が個人的に思うのは、せっかく質問の時間がもらえたのだから、合格するための質問ではなく
この会社に入ると考えた時に、自分自身が本当に確認したいことを聞いた方がいいと思います。
これまで考えていた外から見た企業のイメージと、「働くこと」を前提として企業を見るのとでは、着目するポイントも変わってくるはずです。
面接では、選ばれているのは紛れもない事実ですが
同時に、「自分自身も働き甲斐のある企業を探し、企業を選んでいる」という気持ちを忘れないように面接に挑んでください。
9.面接の中で自身の評価を非常に気にする・求める
ここ数年は、面接の最後に「質問がありますか?」と聞くと、「自分の今回の面接の評価はどうだったか」と質問する方が増えました。
聞いてもらうのは構いませんが、そこで良い評価を伝えたからといって、面接に合格しているわけではないので、これを聞くことの意味を自身の中でよく考えましょう。
せっかくの限られた面接時間を使い何を伝えるのか・表現するのかをよく考えてきている人は、非常に時間の使い方が上手です。
あえて聞くのであれば、次回の面接に向けての改善ポイントを教えてもらった方が、有益だと思います。
聞いた結果、厳しいフィードバックを受けるかもしれませんが、それに気がつかないまま、就職が決まらないことが一番避けるべき事態ですね。
10.そもそもエントリーする会社が少なすぎる
これは、超売り手市場の弊害なのですが、5社未満しか受けていませんという人が増えています。
内定はもらえるかもしれませんが、これは将来をギャンブルに近い形で決めてしまっていると思います。
「内定を取る」という目標は達成できても、本当に自分自身に合う企業なのか、本当に自分がやりたい仕事なのか
数社を見ただけで判断するのは、とてももったいないですね。
また、冒頭にも書きましたが、新卒の就活は、タイミングが決まってしまっているので、タイミングを逃すことイコール失敗につながる可能性が高くなります。
エントリーシートを出すタイミングを逃していたら、2次募集・3次募集があれば、リベンジのチャンスはありますが、なければその企業には新卒では入れないという結果になります。
また、2次募集・3次募集というのは、1次募集で採用できなかった分を補うために実施される企業が多いため、1次募集より圧倒的に枠が少ないケースが多いので、この点も注意したいですね。
そういった事態を避けるためにも、新卒での就職活動という一生に1回しかない機会を有効に使うためにも
納得いく数の会社に応募することをオススメします。
また、エントリーする数が少なく、面接にも慣れていない状態で、本命にチャレンジするのは非常に危険です。
就職活動は、一部は慣れとテクニックです。これは訓練すれば誰でもできることなので、こういったところでつまづかないようにしておきましょう。
私自身は、就職氷河期だったこともあり、100社エントリーして、70社の面接を受けました。
当時はクラブ活動・アルバイトもしながら就職活動をしていたので、相当ハードでしたが
もともと全く注目していなかった隠れ優良企業(自分の中ではノーマークだったので)に就職が決まり、15年以上経った今でも自分に合っている企業を選べたという確信があります。
近年では転職市場も活発なので(コロナの影響で冷え込むかもしれませんが)、転職することも一つの選択肢ですが、自分に合った企業で長く働くのも悪くないと思います。
まとめ
これまで就職活動対策で面倒を見てきた人たちにも共通していますが
就職活動がうまくいかない理由は
- 準備不足(自己分析不足・企業研究不足等)
- 自分自身の思い込みで突っ走っていて自身を客観視できていない
ほとんどこの2つに尽きます。
就職活動は、客観的に自分がどう見えるのかという点にフォーカスし、上手に自身を表現してくださいね。